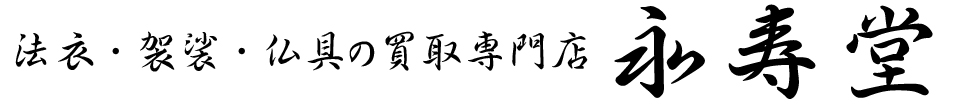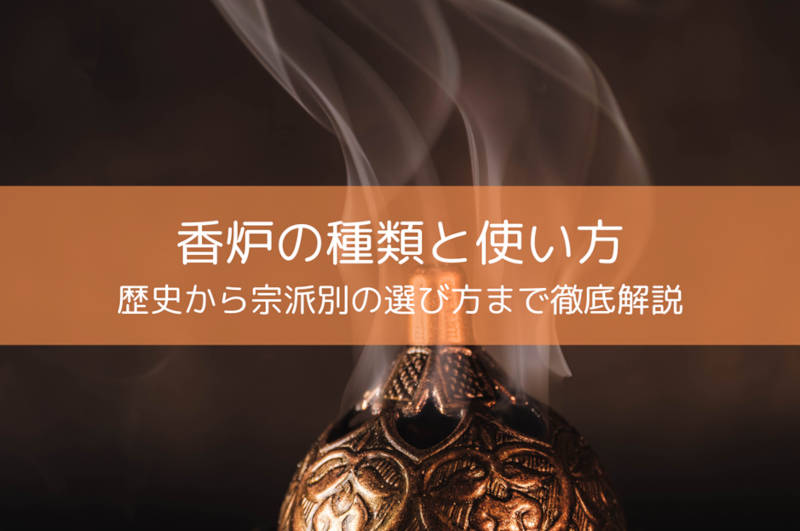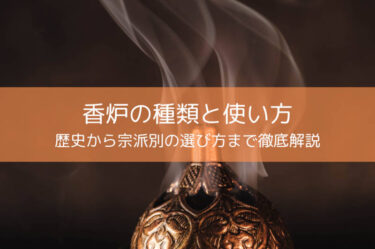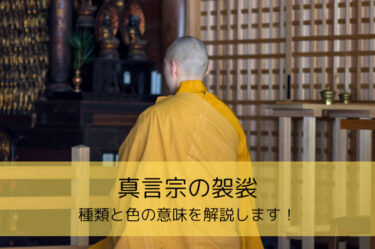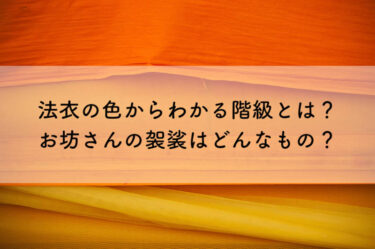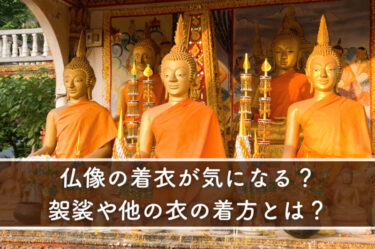香炉は、日本の伝統文化の一部として、古くから生活に取り入れられてきました。
その用途は宗教的な儀式だけでなく、日常生活の中でも広く親しまれています。
この記事では、香炉の歴史や種類、用途について解説し、あなたに合った香炉の選び方を紹介します。
香炉と香の歴史を知ろう
香炉とお香の歴史は、古代インドにまで遡ります。当初、香は仏教の法事に使用され、香炉はそのための器として作られました。
仏教が中国を経て日本に伝わると、香炉も一緒に伝来し、奈良時代には香木が漂着した記録が「日本書紀」に残されています。
インドから中国、そして日本へ
古代インドでは、スパイス文化が発達し、香りを楽しむ習慣が根付いていました。その後、仏教の伝来とともに、香の文化も中国へと伝わり、さらに朝鮮半島を経て日本に到達しました。
日本における香の文化の発展
奈良時代には仏教の影響で香炉が用いられるようになり、平安時代には宮廷文化として香の調合が行われました。「源氏物語」や「枕草子」には、香を楽しむ貴族の姿が描かれています。
香道の確立
桃山時代から江戸時代にかけて、香道が確立され、茶道と並ぶ日本の伝統文化として発展しました。香道は、香の焚き方や香炉の使い方など、細やかな作法が特徴です。

香炉の種類と用途
香炉には、仏壇用、墓用、部屋炊き用など、用途に応じたさまざまな種類があります。それぞれの特徴と使い方を詳しく見ていきましょう。
仏壇用香炉
仏壇用の香炉は、仏前でお香を焚くために使用されます。宗派によって使用方法が異なり、例えば浄土真宗では線香を立てずに寝かせることが一般的です。
浄土真宗の真宗大谷派では「透かし香炉」、本願寺派では「玉香炉」を使用します。器に足が3本ついているものは、1本が手前(私たち側)になるように置きます。これは仏様に対して角を立てないようにするためです。
また、火を使えない場所でも使用できる電池式の香炉もあります。
墓用香炉
墓用の香炉は、墓前でお線香を焚くために使用されます。
墓石に設置するタイプや、屋根付きのものなどがあり、風や雨からお線香を守る工夫がされています。
お墓参りの際には、線香皿を置いてお線香を寝かせることが一般的です。
お墓で使用する香炉は、デザインや材質がさまざまで、持ち運びに便利なものもあります。
部屋炊き用香炉
部屋炊き用の香炉は、日常生活の中で香を楽しむために使用されます。デザインや大きさもさまざまで、インテリアとしても楽しめるものが多くあります。例えば、小ぶりな陶磁器製の香炉や、手作りの焼き物の香炉などがあります。部屋炊き用の香炉は、お香を楽しむための道具としてだけでなく、インテリアとしても優れたデザインのものが多くあります。
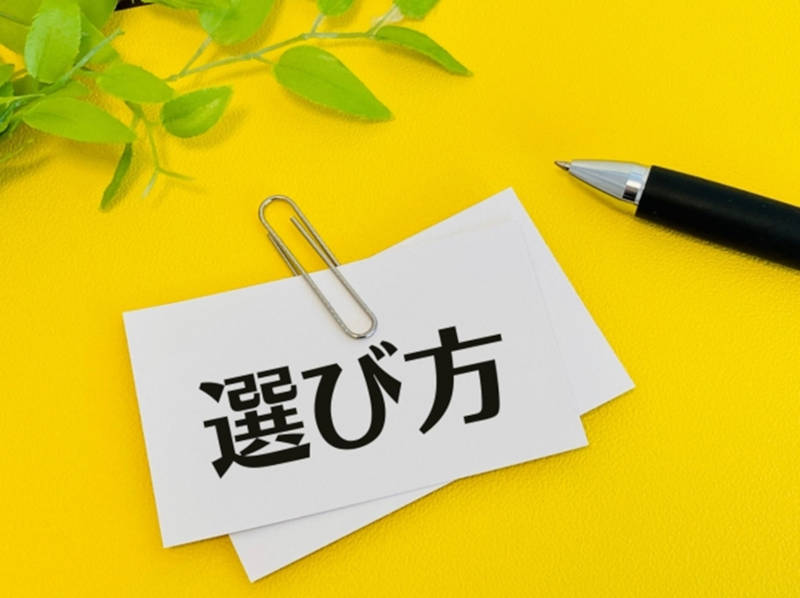
宗派別に見る香炉の選び方
宗派によって、香炉の選び方や使い方には違いがあります。ここでは、特に浄土真宗に焦点を当てて解説します。
浄土真宗の香炉選び
浄土真宗では、土香炉を用いることが一般的です。
真宗大谷派では「透かし香炉」、本願寺派では「玉香炉」を選ぶことが基本とされています。お線香は数本に折って寝かせて供えるのが特徴です。
真宗大谷派では1~2本のお線香を2つか3つに折り、本願寺派では1本のお線香を短く数本に折ります。この違いは宗派ごとの作法に基づいています。
他の宗派の香炉選び
浄土真宗以外の宗派では、一般的に前香炉を用います。お線香を立てて使用し、香炉灰を敷き詰めてから使います。長香炉を選ぶことで、仏壇のデザインや個人の好みに合わせてアレンジすることも可能です。また、宗派によっては香炉のデザインや材質にもこだわりがあり、選び方に注意が必要です。
まとめ
香炉は、その歴史や用途によってさまざまな種類があります。仏壇用、墓用、部屋炊き用と用途に合わせて選ぶことで、より適切な香炉を見つけられるでしょう。また、宗派による違いを理解することで、正しい使い方ができるようになります。
あなたに合った香炉を選び、香の文化を楽しんでみてはいかがでしょうか。
法衣や袈裟や寺院用仏具の買取り専門店

当社は名古屋市に店舗を構えて、法衣や袈裟や仏具や宗教本の買取を承っております。出張買取や宅配買取もしております。
また、遠方の方でも量が多く宅配買取が難しい場合であれば出張買取も承っておりますので、ご不要な法衣や袈裟などの売却やご処分をご検討中の方は、ぜひ永寿堂にお問い合わせ下さい。当店がしっかり買取りさせて頂きます。
永寿堂へのお問い合わせ先
・TEL:0120-060-510
・メール:info@eijyudou.com
・LINE ID:@721crjcp